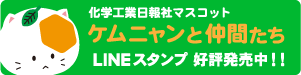第一三共は、新型コロナウイルスワクチンの実用化を機に、自社主導のワクチン事業を本格化する。独自のメッセンジャーRNA(mRNA)技術を応用したコロナワクチンは、3月に最初の臨床試験を開始し、順調に進めば2022年にも供給可能になる。変異種にも対応しやすい国産初のmRNAワクチンとして開発し、原材料や部材は国内で最大限調達するサプライチェーンを確立する。次のパンデミックにも備え、グローバル展開も可能なワクチンメーカーへ成長を図る。
第一三共が開発するコロナワクチンは、ウイルスの設計図(遺伝情報)を合成して投与するmRNAワクチン。最初の第1相臨床試験(P1)は3月中にも始める。すでに行われている他社の国内P1/2と同等の規模、評価項目などで行われる見込み。
海外で接種が始まっている米ファイザー-独ビオンテックや米モデルナのコロナワクチンも、mRNA技術が基盤になっている。両ワクチンは、数万人規模の海外治験で、発症予防効果を示す有効率が95%前後を記録した。第一三共のワクチンも免疫応答のメカニズムは同じであることから、今後の治験で同等の有効性を証明したい考え。
mRNAワクチンは、ウイルスのゲノム配列が分かれば短期間で開発できる。ウイルスが変異してもゲノム情報があれば数週間以内にワクチンを改良できるとされる。変異種に対応してワクチン製剤を改良した場合、薬事手続きを簡素化できる「プロトタイプ・ワクチン」として運用できるかは、薬事当局の判断にかかっているという。
製造体制も準備している。厚生労働省の助成金などを投じ、生産子会社の第一三共バイオテックでmRNAワクチンの製造体制を整備する。目標とする生産能力や供給量などは非開示。具体的な数量をオープンにすると原材料の調達コストや安定供給に影響する可能性がある。有事でも安定供給を確実にするため、原材料や部材を可能な限り国内で調達できるサプライチェーンを確立する。
ワクチンの実用化時期は最終治験の規模や試験デザイン、供給量によって前後するが、すべての開発が順調に進めば、最短で22年中にも供給開始できそうという。
mRNAワクチンは壊れやすいため、長期保存・輸送が難しい。ファイザーらのワクチンはマイナス70度C前後、米モデルナ品はマイナス20度Cの超低温環境が必要だ。第一三共は、流通体制まで視野に入れた安定性試験のデータを蓄積していき、先行品より優位性がある製剤にする。
同社の武下文彦ワクチン研究所長によると、mRNAワクチンの基盤技術は約10年前から社内研究してきた。コロナワクチン開発を通じmRNAワクチンの製造プラットフォームを確立し、次のパンデミックでは、より迅速にワクチンを開発できる基盤を作っておく。コロナ以外のワクチンや治療薬も開発する。
第一三共は他社との提携などを通じてワクチン事業への本格参入を目指してきたが、苦戦している。研究開発や製造で合弁を組んだ北里研究所とは、自主回収や開発の遅れなどが相次ぎ、17年に提携を解消。グラクソ・スミスクライン(GSK)との販売子会社も19年に終了した。北里との合弁から引き継いだ資産を生かしながら、今後は第一三共が主体的にワクチン事業を手がけていく。
丹澤亨ワクチン事業部長は、「(北里から)第一三共本体に移ったことで、ワクチンメーカーとしてグローバルに飛躍していくことは視野に入っている」と話す。まずはコロナワクチンを日本に早期供給する目標を達成し、グローバル展開に向けたビジネスモデルを構築していく。