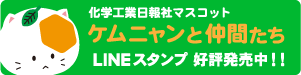日清紡ホールディングスが事実上、デニム生産事業から撤退した。インドネシアの合弁を解消し、相手企業への株式売却を終えた。カイハラ、クラボウと並ぶ、かつての3大デニムメーカーの雄は、静かにその幕を閉じる格好となった。
デニム生地が使われるジーンズは、日本のファッション業界で一際輝いた存在だった。中国を中心とした衣料品の輸出が増えるなか、生地生産から縫製、販売にいたるまで、日本国内で完結可能なビジネスだった。しかも日本製のジーンズは海外から高く評価され、輸入品としても存在感を発揮していた。
その日本で“プレミアムジーンズ”のブームが到来したのが2000年代初頭のこと。当時の米国はサブプライムバブルの真っ只中。多くのセレブが1本2万円以上するようなジーンズを身につけ、そのファッションが日本にも飛び火した。日系のジーンズ関連メーカーもこぞってブームに乗じ、これまでの3倍以上も値の張るジーンズが持てはやされる結果となった。高級品を作れば作るだけ売れた時代。年配の業界人は、美空ひばりの歌に掛けて「“藍、燦燦(さんさん)”と輝く時代だった」と当時を懐かしむ。
リーマンショックを契機に、この空前のブームは終焉を迎えるが、結果として、このブームがジーンズ業界自体の首を絞めた。一つは「ジーンズであること」にあぐらをかいたこと。ある縫製業者は当時、1本3万円もするデザイナージーンズを手に取るやいなや「こんな作り方をしていてはジーンズ業界自体が衰退する」と喝破した。また従来のゴワゴワした風合いのデニムにこだわった結果、着用感をないがしろにした商品開発が続けられた。いわゆる典型的なプロダクト・アウトの手法である。以降、業界人の言葉を借りれば「“藍、散々”の時代」に突入する。
衣服に求める市場の要求が、吸水速乾や伸縮性などの快適性へ移行するなか、その時代の変化にジーンズ業界は対応できなかった。本来であれば、デニム生地にストレッチ性などを持たせることは、日系メーカーが得意とする技術であったにも関わらずだ。
ジーンズ業界の栄枯盛衰に触れただけでも、先を見通す目と業界の常識を疑うことの重要性を知ることができる。日清紡の撤退を惜しむ声は多いが、不採算部門を切り離して身軽になったのも事実。今では燃料電池用のセパレーターや白金代替の触媒など、今後が期待される事業も数多く手掛ける。かつてのデニム同様、燦燦とした輝きを放つことを期待したい。
【社説】研究者の挑戦心 育み見守る土壌を
9/30