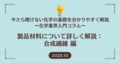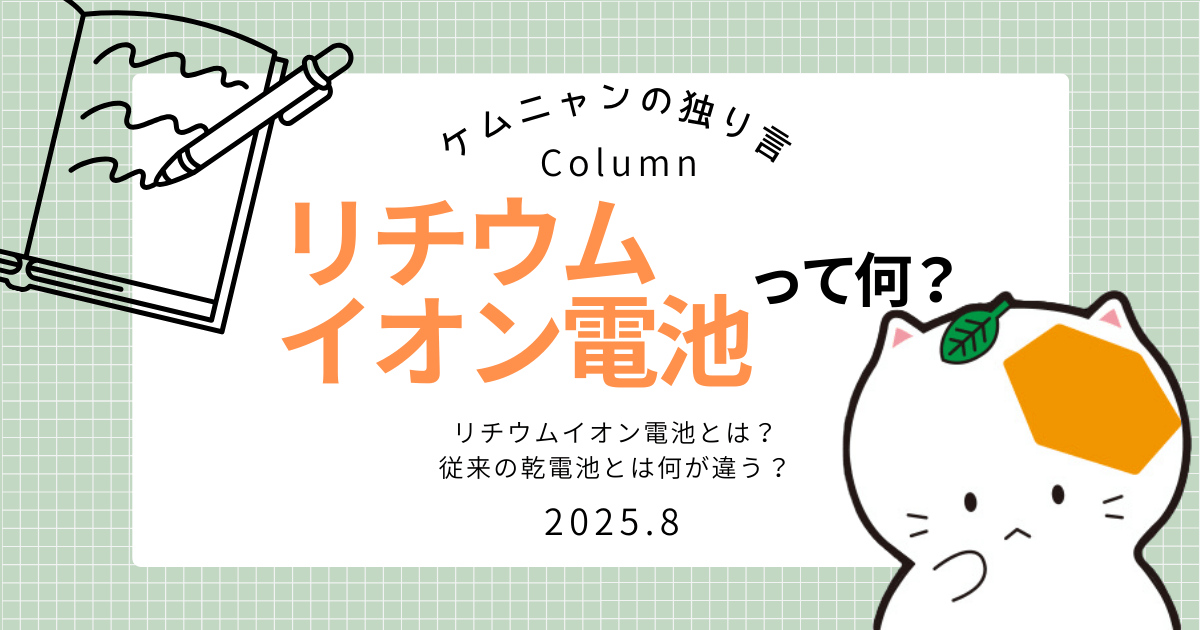
リチウムイオン電池とは?従来の乾電池とは何が違う?
現代のスマートフォンや電気自動車、さらには宇宙開発や医療機器に至るまで、幅広い分野で利用されている「リチウムイオン電池」。持ち運びやすく、繰り返し使えるこの電池は、従来の乾電池とは大きく異なる特徴を持っています。本記事では、リチウムイオン電池の仕組み、用途、乾電池との違い、そして今後の展望や課題などを解説します。
リチウムイオン電池について、存在は知っているけど実はあまりよく分かっていなかったという方におすすめのコラムです。
リチウムイオン電池とは?その仕組みをやさしく解説
リチウムイオン電池(Li-ion battery)は、充電して繰り返し使える二次電池の一種で、1991年にソニーが世界で初めて商用化しました。小型で高性能な電源として、瞬く間に携帯電話やノートパソコン、カメラなどに普及し、現在では脱炭素社会の中核技術として注目されています。
※リチウムとは、レアメタルの一種で供給リスクや偏在性が高い金属資源に属しています。レアメタルについて知りたい方はこちらのコラムもおすすめです。
「実は知らない?レアメタルの基本を解説」
構造は主に以下のようになっています。
正極:リチウム金属酸化物(LiCoO₂など)
負極:グラファイト(炭素)
電解液:有機溶媒に溶かしたリチウム塩
セパレーター:正極と負極を隔てる絶縁膜
充電中にはリチウムイオンが正極から負極へ移動し、放電時には逆方向に戻ることで電流が発生します。この「イオンの移動」が、リチウムイオン電池の名の由来です。
従来の乾電池とは何がちがう?
乾電池は「一次電池」と呼ばれ、一度使い切ると再利用できないのが特徴です。対して、リチウムイオン電池は「二次電池」であり、数百〜数千回の充電と放電を繰り返すことが可能です。
比較項目 | 乾電池(一次電池) | リチウムイオン電池(二次電池) | |
|---|---|---|---|
再利用性 | ×(使い切り) | リチウムイオン電池(二次電池) | |
電圧 | 約1.5V | 約3.6〜3.7V | |
エネルギー密度 | 低い | 高い | |
重量 | やや重い | 軽量 | |
液漏れ | 起こりやすい | 起こりにくい(設計次第) |
※正極にリチウム金属酸化物、負極に炭素系を使用した場合
乾電池はリモコンや時計など低電力製品に適していますが、高出力・高効率が求められる現代機器にはリチウムイオン電池が不可欠です。
「乾電池」という名前の由来とは?

話は逸れますが、ここで豆知識をひとつ。そもそも「乾電池」の「乾」とは何を意味しているのでしょうか?
19世紀のボルタ電池などは、液体の電解液を使用した「湿式電池」でした。これに対し、1887年にドイツのカール・ガスナーが開発した乾電池は、電解液をペースト状にして液漏れを防ぐ構造を採用しました。このことから「乾いている=乾電池」と呼ばれるようになったのです。
電池の歴史に見る技術の進化
電池の歴史は、およそ200年以上前から始まったとされています。ただし、もっと古い時代にすでに電池のようなものが存在していた可能性も指摘されています。
たとえば、20世紀に入ってからイラクのバグダッド近郊にあるパルティア時代の遺跡から出土した素焼きの壺が、「バグダッド電池」と呼ばれ話題となりました。この壺の中には銅板と鉄棒が挿入されており、酸性液を注ぐことで微弱な電流が発生するとされています。真偽は学術的に議論が分かれていますが、もし本当に発電目的だったとすれば、2000年以上前に電池が存在していた可能性があるのです。
その後、近代的な電池の起源は19世紀初頭にさかのぼります。ヨーロッパで金属と電解液を用いた「湿式電池」が登場し、やがて改良が加えられた電池が通信機器や化学実験などに活用されるようになります。
さらに、19世紀後半には電解液をゲル状に固めて持ち運び可能にした「乾式電池」が開発されます。20世紀初頭には、日本でも屋井先蔵らによって乾電池の国産化が進み、軍事・民生の両面で広く普及していきました。
そして20世紀後半には、より高性能な充電式電池としてニッケル水素電池やリチウムイオン電池が次々に登場します。リチウムイオン電池の商用化によって、携帯電話やノートパソコン、EVなどの分野で電池技術は飛躍的な進歩を遂げました。
このように、電池は人類の生活と産業を根底から支える技術として、時代とともにその姿を変え続けてきたのです。
リチウムイオン電池の主な用途

リチウムイオン電池は、以下のように多様な分野で活用されています。
家庭・IT機器
スマートフォン、ノートパソコン、タブレット、携帯ゲーム機
ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ
産業機器・モビリティ
電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)
電動アシスト自転車、電動工具
宇宙開発
国際宇宙ステーション(ISS)や探査衛星でも、軽量かつ長寿命なリチウムイオン電池が使われています。真空や極寒といった過酷な環境でも安定した性能を発揮することが求められます。
医療機器
携帯型除細動器(AED)
人工心臓の電源
携帯用点滴ポンプや内視鏡カメラ
ドローン・ロボティクス
小型ドローンのバッテリーとして軽量性・高出力が重宝
サービスロボット、AGV(自動搬送車)の電源
このように、リチウムイオン電池は未来の技術インフラの中心とも言える存在です。
リチウムイオン電池の課題と今後の展望
いくら高性能とはいえ、リチウムイオン電池には無視できない課題もあります。
発火・爆発リスク
リチウムは非常に反応性が高く、過充電・短絡・高温状態では発火の危険性があります。そのため、製品には保護回路(BMS)を内蔵するなど、安全対策が不可欠です。
リサイクルと環境負荷
使い終わったリチウムイオン電池の回収・再資源化が重要な課題です。現在はコバルトやリチウムの回収技術が進展していますが、回収コストや処理技術の高度化が求められています。
次世代技術:全固体電池との関係
次世代の「全固体電池」は、液体の電解質を固体に置き換えることで、安全性・エネルギー密度・充電速度のすべてを向上させると期待されています。これにより、発火リスクが低減し、より小型で高性能な電池が実現可能です。現在、トヨタやパナソニックなどが量産化に向けて研究を進めています。
まとめ:未来を支える電池技術
リチウムイオン電池は、単なる便利な電池ではなく、持続可能な社会を支える基盤技術です。乾電池と比較すると構造も性能も飛躍的に進化しており、宇宙から医療まで活用範囲は年々拡大中です。一方で、安全性やリサイクルの課題もあるため、次世代の全固体電池や新素材開発への期待も高まっています。
電池の進化は、私たちの未来の生活スタイルそのものに直結しています。今後もその動向に注目していきましょう。
化学工業日報 電子版
化学工業日報電子版では、リチウムイオン電池に関連する記事を多数掲載しています。
電子版は平日毎日更新。
リチウム化合物特集 供給過多で価格下落
https://chemicaldaily.com/archives/641443
新電元工業、通信設備向けLiBシステムの受注開始
https://chemicaldaily.com/archives/668421
電子版は会員サイトです。ご購読で鍵付き記事を閲覧頂けます。
1ヶ月の無料トライアルを実施中。