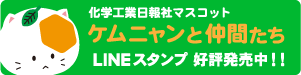パナソニックが太陽電池(PV)生産からの撤退を決めた。世界で高いシェアを握っていた2000年代初頭、同社(当時は三洋電機)のPV「HIT」は、業界関係者にとって憧れの的だった。HITは、結晶シリコン基板とアモルファスシリコン膜を組み合わせた独自の構造で、高い変換効率が特徴だ。10年代前半に日本市場に参入を果たした外資系PVメーカーも、HITの開発動向をつぶさに観測。同メーカーのセールスマンが「当社のPVよりもはるかに性能が良い。わが家に取り付けるならHITを選ぶ」と、その技術力に脱帽していた姿が印象的だった。
しかし、あれから約10年が経過した今、中国には日本の1年間の総需要量を1社で作り出すことのできるガリバーメーカーが複数存在する。圧倒的な生産規模によるコスト効果の前に、性能だけで太刀打ちできる状況ではないことが明白だった。
しかも性能も、今や中国を中心とした海外勢がトップを走る時代となった。再生可能エネルギー固定価格買い取り制度(FIT)が施行された12年、PVパネル1枚当たりの出力は250ワット前後だった。業界では300ワット超えが一つの目標とされるなか、韓国のハンファQセルズが16年に300ワット時代の口火を切って以降、出力は飛躍的に向上した。20年には500ワットとなり、21年は業界大手の中国トリナソーラーが600ワット品の市場投入を予定するなど、今後は600ワット超の時代へ突入すると予想されている。
苦戦を強いられている日本勢はパナソニックだけではない。三菱電機は自社ブランドのPV製造を終了。京セラも、このほど発表した20年4~12月期決算によると太陽光発電システムの販売低迷が続いている。価格と性能の両面で大きく引き離される現状にあって日本勢が生産の撤退、あるいは規模の縮小を決めることは当たり前の決断といえるだろう。
しかし太陽光発電は、地球環境を維持していくうえで、なくてはならないエネルギー源だ。PVメーカーが本気で再生可能エネルギーを広めたいなら、色素増感型や有機薄膜、多接合などの次世代PVの開発に特化するか、安価で信頼性の高いシステムを構築・提案する以外に生き残る道はない。その際、屋根や土地に限定するのではなく、自動車や建物壁面など適用範囲の拡大を図ることが、さらなる普及拡大のカギを握る。
日本のPV業界にとって、PVは作るものではなく、使いこなすものになった。パナソニックの今回の撤退劇は、そんな時代の幕開けといえる。