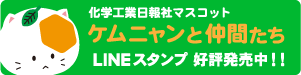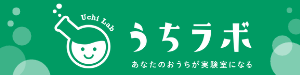ロシアのウクライナ侵攻で原材料価格の高騰が懸念材料として残るなか、新型コロナウイルス感染は流行期の第7波に入り、消費抑制に追い打ちをかけかねない。世界的な物価高、これにともなう米国の金利上昇など経済環境への影響も懸念される。参院選で大勝して信任を得た自民党が公約に掲げる物価高対策の早期実施が期待されるところだが、山積する課題への効果は不明。しばらくは不透明ななか、手探り状態が続く。
原材料高騰分の製品価格転嫁は、いぜん重要課題だ。帝国データバンクが6月に実施した企業の値上げに関するアンケート(複数回答)では、自社の主な商品・サービスに関して今年4月以降に値上げした、もしくは値上げする企業は68・5%で全体の7割近く。また6月以降に値上げした、もしくはする予定の企業は全体の37・0%を占めた。7~9月頃に値上げ予定の企業は19・9%と、今年4月に実施した同様の調査と比べ10ポイント超上昇。急激な原材料高騰に対する危機感の高まりがうかがえる。
4月以降に値上げを実施ずみ、あるいは予定する企業を業界別でみると卸売が87・6%、製造が79・9%で全体平均を10ポイント超上回った。一方、情報サービスや運輸・倉庫といった業種は値上げ実施の割合が低かった。
この間のコスト高による企業の収益力低下が懸念されるところだが、人流の復調にともなう対面型ビジネスの回復など業種により改善傾向にある。ただ新型コロナの第7波は8月にピークを迎える見通しであり、予断を許さない。重症化率の低さから、まん延防止等重点措置といった行動制限は今のところないとされるが、全国を対象に7月前半から実施を予定していた「全国旅行支援」が延期されるなど、観光業界の需要底上げの手段は遠のいた。
原材料高騰に加えて急激な円安による輸入コストの上昇もあり、秋にかけて食料品などの値上げラッシュが予想されている。個人消費の足を引っ張ることになれば関連業界への影響も大きくなる。
原油・原材料価格の高止まり、先が見通せないウクライナ情勢、円安進行にともなう輸入物価の上昇といった懸念材料が山積するなか、今後は一層の価格修正が必要となる場面も出てこよう。化学企業などは市況上昇といったプラス要因があるものの、価格転嫁のタイミングを失うと収益力を低下させ、経営基盤の脆弱化につながる。先が読みづらいなかで安定した基盤を確保するには、収益性の高い付加価値品に力を入れるとともに、環境変化に迅速対応する経営判断が求められる。