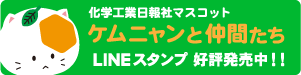3月21~22日、東京電力と東北電力管内を対象に「電力需給逼迫警報」が初めて発令された。広範囲での停電の恐れが強まったことで企業や家庭に節電が要請され、管内に事業所、工場を構える化学企業も対応に追われた。突然の警報発令で、11年前の東日本大震災後の停電の記憶がよみがえった人も多いだろう。
折しも、ウクライナ情勢を巡り原油や天然ガスなどエネルギー・資源価格が上昇、エネルギーの供給不安が強く意識されていたなか、警報が重なった。経団連の十倉雅和会長(住友化学会長)は、22日の定例会見で「エネルギー安全保障の重要性が再認識された」と述べた。
一連の出来事はエネルギー安全保障とカーボンニュートラルを、どのように両立させるか議論するうえでも重要になる。昨年10月に閣議決定された「エネルギー基本計画」は、電源構成に占める再生可能エネルギーの比率を19年度の18%から30年度に36~38%まで高める目標を掲げる。ただ再エネは天候など自然条件に左右される。昨年来の欧州での天然ガス価格上昇は、エネルギー政策の転換による石炭から天然ガスへの切り替えが急速に進んだことも一因とされる。国内でも普及に向けた動きが進む水素やアンモニアといった次世代エネルギーには、既存燃料に比べ割高なコストをどう下げるかなど越えるべきハードルがある。
東日本大震災以降、日本では原子力発電に関する議論はほとんど停滞したままだ。エネルギー基本計画では、電源構成に占める原発の比率を19年度の6%から20~22%に高める目標を示すが、震災後に再稼働したのは33基中10基。経団連の十倉会長も「安全性が担保され、地元住民の理解が得られた原発については、速やかに再稼働させる必要がある」と訴える。
欧州では、カーボンニュートラルやウクライナ情勢を受けてフランスが原発6基の新設計画を公表し、ベルギーも25年に閉鎖予定だった原発2基の10年間の稼働延長を決めた。日本では現状、原発の建て替えなどの方針は示されていないが、エネルギー政策に詳しいある学識者は「原発の建て替えを行い、エネルギー源の多様化の選択肢を残すべき」と指摘する。
仮に現在の33基が法律上限の60年の稼働延長が認められても、稼働可能な原発は2050年に18基、60年には5基まで減るとされる。カーボンニュートラルの潮流が押し寄せて地政学リスクも高まるなか、エネルギー政策の不作為を続けるわけにはいかない。将来を議論するために残された時間が限られることを、国も政府も認識すべきだ。